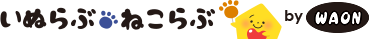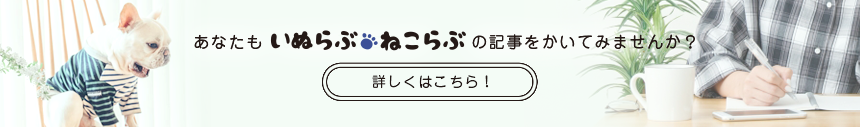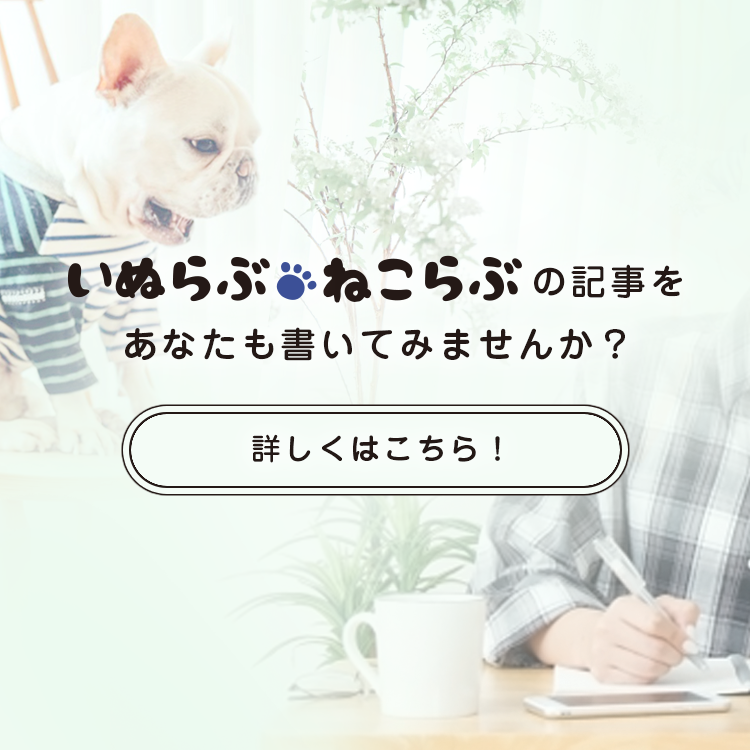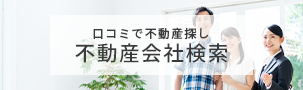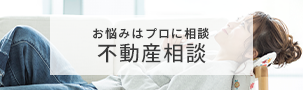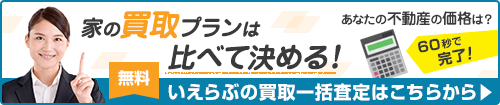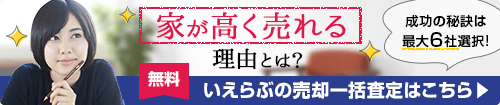目次

ヘルプマークとは、外見からは判断できない配慮や助けを必要としている方が、そのことを周囲に知らせることのできるマークです。
見えない障がいを抱えた方が、援助を受けやすくなることを目的に作成されました。
マークにより可視化することで、見えない障がいへの理解が広がるとして、東京都をはじめ、今では全国に普及しつつあります。
今回は、ヘルプマークの受け取り方や自治体の取り組みなどをご紹介していきます。
ヘルプマークの利用を少しでも考えている方や、各自治体の活動が気になるという方におすすめの記事です。
ヘルプマークの対象者は?どんな効果があるの?
ヘルプマークの主な対象者はこちらです。
- 義足や人工関節を使用している方
- 内部障がいや難病の方
- 妊娠中の方
- 精神疾患の方
- 高齢者
- その他ヘルプマークの利用を希望する方
対象は、障がい者と認められている方だけでなく、配慮や援助を必要とする全ての方です。
社会生活のなかで、配慮や援助が必要だと感じたら、ヘルプマークを受け取ることができます。
身につけることで、電車やバスで席を譲ってもらったり、突発的な事態に困っている際、声をかけてもらえるなどの配慮が期待されています。
外見からは分かってもらえなかったSOSのサインを、周りの人に知ってもらえるというのは、安心感が違いますよね。
ヘルプマークの受け取り方・配布場所について
ヘルプマークの受け取りに、特別な基準が定められているわけではありません。
障害者手帳や診断書なども必要なし。
(※一部自治体では申請書の提出が必要になる場合があります)
これは、ヘルプマークを必要な方が円滑に利用できるよう、配慮が行われているためです。
マタニティーカードと同じように、家族が代理で受け取ることも可能です。
配布場所は、各自治体により異なります。
都内では、駅務室、バス・電車の営業所、病院や福祉施設などでヘルプマークを配布しています。
地方の各自治体では、区役所や福祉センターで配布していることがほとんどです。
一部自治体では、郵送で受け取ることもできます。
お住まいの自治体のホームページを確認してみてくださいね。
ヘルプマークを作る方法
ヘルプマークを使いたい!
しかし、配布場所が遠かったり、受け取りに行くことができないという方もいると思います。
じつはこのヘルプマーク、自分で作ることができるんです!
本人が使用する分には、特別な申請も必要ありません。
東京都福祉保健局の「作成・活用ガイドライン」にしたがって作成しましょう。
ツールダウンロードはこちらから。
※著作権がありますので、自作したものを他の人へ販売するなどしてはいけません。
ヘルプカードとは
ヘルプマークはストラップがついていて、他人から見えやすいバッグなどに下げて使うタイプ。
一方、ヘルプカードは、必要なときに取り出して使用する携帯型のカードタイプとなっています。
カードには、緊急連絡先や支援してほしい内容を記載できます。
日常生活では席を譲ってもらうなどの配慮は必要ないが、緊急時や災害時には何らかの援助が必要という方におすすめ。
また、ヘルプマークに個人情報を載せるのは不安があるという方も、連絡先はヘルプカードに記載し、ヘルプマークと併用して使うこともできます。
各自治体の取り組み

<全国のヘルプマーク・ヘルプカード配布状況>
平成24年に東京都が作成したヘルプカード。
平成29年には案内用図記号に追加されて、全国への普及が本格化しました。
令和元年9月30日現在、1都1道2府37県に広がっています。
(参考元:東京都福祉保健局)
ヘルプマークやヘルプカードをはじめ、バッジ型やシールタイプを配布している自治体もあります。
また、県をあげて積極的に普及活動を行っている地域も。
このように、自治体によって、種類や普及活動もさまざまな形があります。
ここでは、その取り組みの一部をご紹介します!
<神奈川県>
平成29年3月からヘルプマークを導入。
令和元年10月からは、「LIMEX」を使用したマークに変わりました。
LIMEXとは、石灰石からうまれた新素材で、リサイクルできることから環境にいいとされています。
また、破れにくく、水に濡れても大丈夫なので、雨の日でも安心。
薄くて手軽な素材で、カードにケースに入れて使うこともできるんだとか。
環境に配慮し、より使いやすくアレンジされたヘルプマークは、工夫を凝らした取り組みといえます。
<愛知県>
愛知県では、平成30年6月4日から、「ヘルプマーク普及パートナーシップ制度」を創設し、ヘルプマークの普及活動に協力していただける民間企業、法人、団体を募集しています。
この制度に登録すると、企業名が県のウェブページに公表され、「障がい者支援に理解のある企業」としてPRすることが可能。
実際、愛知県のウェブページにはさまざまな普及活動が、企業名とともに紹介されていました。
主な普及活動
- セミナーやイベント、社内広報誌でのヘルプマークPR
- 社内研修にてヘルプマークの勉強会を開催
- 駅周辺や空港にてヘルプマークのロゴ入りティッシュ配布
令和2年3月末現在、221の事業所が登録し、普及の取り組みを広げています。
稲沢市では、災害時の「障がい者支援用バンダナ」にヘルプマークを載せることで、一目で支援が必要だと分かるような仕様に活用しました。
岡崎市では、平成30年1月15日からシールタイプの配布を開始。
カバンなどに下げる場合は、市販のカードケースに入れて使います。
シールタイプのいいところは、車に貼れるところ。
車でおでかけすることが多い、地方ならではの視点といえそうです。
<長野県>
平成30年7月からヘルプマークの配布を開始。
普及活動としてテレビCMを作成し、令和元年7月から9月にかけて地上波にて放映しました。
CMは当事者が出演し、ありふれた日常生活のなかでヘルプマークの意味を訴える内容となっています。
また、ウェブサイトでは、県内の高等学校放送部が制作したPR動画も公開されており、普及活動の紹介も充実しています。
長野県では、配布以前から「長野県ヘルプマーク普及協会」が活動をしており、団体の取り組みも積極的に行われています。
<兵庫県神戸市>
平成30年3月12日より、ヘルプマーク・ヘルプカードの配布を開始しました。
区役所や福祉センターなどでの配布を行っていましたが、平成31年3月からは配布場所を拡大。
地方で初めて、ヘルプマークを駅で配布する取り組みをはじめました。
区役所の窓口に比べ、駅はよく利用するし、気軽に立ち寄りやすいですよね。
駅でヘルプマークを受け取ることができるのは、嬉しいポイントといえます。
令和2年4月現在、神戸市の配布場所はこちら
・ 各区役所、支所 健康福祉課(保健福祉課)あんしんすこやか係
・ 西神中央出張所保健福祉サービス窓口
・ 障がい者福祉センター(総合福祉センター内)
・ 神戸市営地下鉄(西神・山手線、海岸線)各駅窓口
・ 市バス・地下鉄お客様サービスコーナー
・ 神戸市総合インフォメーションセンター
・ 障がい者地域生活支援センター、障がい者支援センター

東京都福祉保健局では、その他の自治体の取り組みも掲載しております。
ぜひ、ご覧ください。
障がい者グループホーム「わおん」の取り組み

株式会社アニスピホールディングスでは、援助や配慮を必要とする方々の環境づくりをサポートしたいという思いから、ヘルプマークとタイアップさせていただくことになりました。
都営浅草線の優先席エリアに、タイアップした広告ステッカーが掲出されています。
殺処分を救うためうまれた、ペット共生型グループホーム「わおん」を多くの方々に知っていただきたい。
そして、ヘルプマークの普及啓発に貢献したいと考えています。
掲出期間は2021年3月2日までとなっております。
ぜひ、チェックしてみてくださいね。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
ヘルプマークの普及・利用は、見えない障がいへの理解につながります。
そして、それは「さまざまな人々が暮らしやすい社会」を実現することにつながります。
困ったことがあれば助け合う。
ヘルプマークは、人間関係で大切なことを思い出させてくれるやさしいマークなのです。