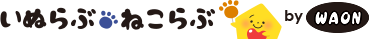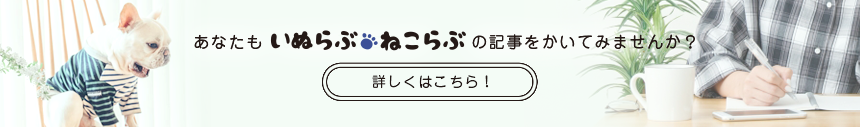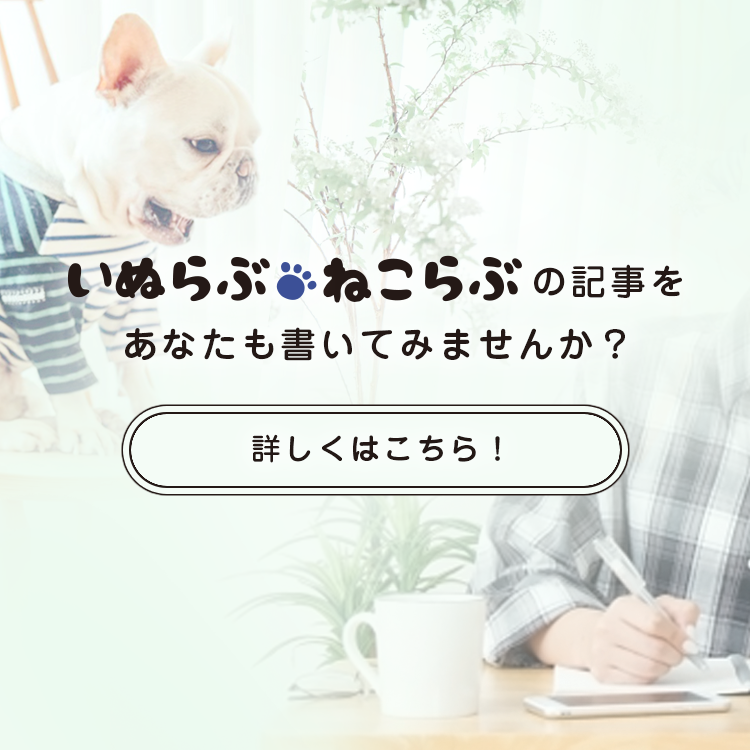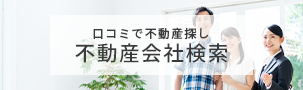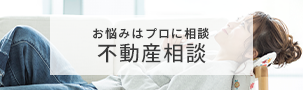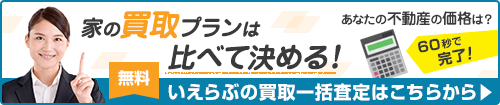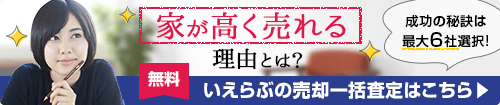目次

動物とふれあうことで癒されたという経験がある方も多いのではないでしょうか?
その癒しの効果は科学的に認められ、医療・福祉・介護の現場で応用されています。
その一つとしてあげられるのが、「アニマルセラピー」という療法です。
日本ではまだあまり広まっていませんが、アニマルセラピーとは、ストレス緩和や、生活の質を回復させることを目的として、人と動物をふれあわせる療法のことを言います。
高齢者や精神疾患、自閉症などに効果があるとして、アニマルセラピーは人の健康を支える療法として可能性を秘めています。
今回は、アニマルセラピーでも代表的なセラピー犬を中心にご紹介します。
アニマルセラピーで活躍!セラピー犬について
<セラピー犬とは?>
セラピー犬とは、その名の通り、アニマルセラピーのお仕事をする犬のことです。
基本的なしつけはもちろん、人とふれあうのが好きで、忍耐力が強いという特徴を持っています。
基本的にはどんな種類の犬でもセラピー犬になることができます。
医療・福祉・介護をはじめとして、教育現場や、刑務所、被災地へ訪問などが主な活動場所となっています。
医療現場では、主にリハビリの場面で活躍していますよ。
福祉・介護の現場では、高齢者施設などで元気を与える活躍をしています。
<セラピー犬になるには?>
セラピー犬になるには、民間の団体が実施している認定試験に合格し、資格を取得しなければなりません。
受験資格は、
- 生後8ヶ月以上
- ワクチン接種が済んでいること
- トイレのしつけができている
などがあります。
認定試験に合格するためには
- 基本的なしつけができていること
(おすわり・マテ・無駄吠えをしない)
- 触られても嫌がらないこと
(知らない人に触られたり、とつぜん後ろから触られたりしても受け入れられる)
- 落ち着いて行動できること
(車いすなどの見慣れないものや、大きな音に対しても焦らずに対応できる)
- 我慢できること
(動物の触り方に慣れていない人から強く触られても我慢できる)
- 他の犬ともなかよくできること
などの条件があげられます。
セラピー犬になるまで~トレーニングをご紹介~

セラピー犬になるには訓練も必要です。
つづいて、その訓練の一部を紹介します。
- アイコンタクト
文字通り、人と犬が目を合わせることを言います。
しつけの基礎であり、主従関係を築くためにもアイコンタクトは大切だといわれています。
犬はアイコンタクトを通して信頼関係を深め、相手の気持ちや体調を感じ取ったりしています。
- 同速歩行(ヒール)
相手のペースに合わせ、隣で同じスピードで歩くことを言います。
こちらは訓練の基礎であるといわれています。
人が歩く邪魔をしないよう適切な距離を保ちつつ、左側で一緒に歩きます。
早足やゆっくりな速度に対応することはもちろん、障害物がある場合の歩行も訓練します。
医療・福祉・介護の現場では、杖をついていたり、車イスに乗っていたりと速度を合わせる相手はさまざまです。
車イスとの同速歩行は、ブレーキの音を聞き分けたり、エレベーターに乗ったり、車輪に巻きこまれないよう気をつけたりと決して簡単ではありません。
- ケインウォーク
主に、高齢者と同速歩行することを言います。
特に遅い歩行に合わせる訓練です。
訓練では、杖をついてゆっくり歩き、犬に速度を理解させます。
また、中には棒で虐待を受けていた犬がセラピー犬になる場合もあります。
過去に棒でたたかれたことがある場合は、杖を怖がるので、それを一緒に乗り越えるのもトレーニングのひとつです。
高齢の方や杖をついて歩く方はもちろん、ケガや病気の後遺症がある方に合わせて歩く訓練もします。
速度だけでなく、不規則な動きにも合わせられるようにするためです。
- ベッドマナー
最終段階の訓練で、ベッドマナーを学びます。
こちらは、寝ている人への対応として必要になる訓練です。
部屋へ入るところから、ベッドのうえでの動き、ベッドから離れるとき、部屋を出るところまで一連の動きを身につけます。
アニマルセラピーの効果について
個人差はありますが、アニマルセラピーには
- 精神的効果
- 身体的効果
- 社会的効果
があるとされています。
アニマルセラピーの効果の一例は以下のようになっています。
- ストレス軽減
- 高齢者の孤独感を減少
- 抑うつ症状の改善
- 自発性の向上
- 動くことの意欲向上による身体的リハビリ補助
- 会話が増えることによる発声のリハビリ補助
- 世話をすることで身体活動量が増える
- 世話をするという役割の芽生え
- 介護施設におけるコミュニケーションが増える
- 被災地における他人同士の会話の潤滑油になる
また、アニマルセラピーの体験談としては
- 「可愛かった」「また来てほしい」と表情が明るくなった。
- 昔犬を飼っていたからとても懐かしく、感動した。
- 大好きな動物に会えると思うと嬉しく、リハビリも頑張ろうという気持ちになれる。
- 一緒にお散歩するのが楽しくて、気づいたら歩くスピードがあがっていた。
といった声も多く、3つの効果の中でも、とくに癒しによる精神的効果が大きいといえそうです。
アニマルセラピーの活躍について
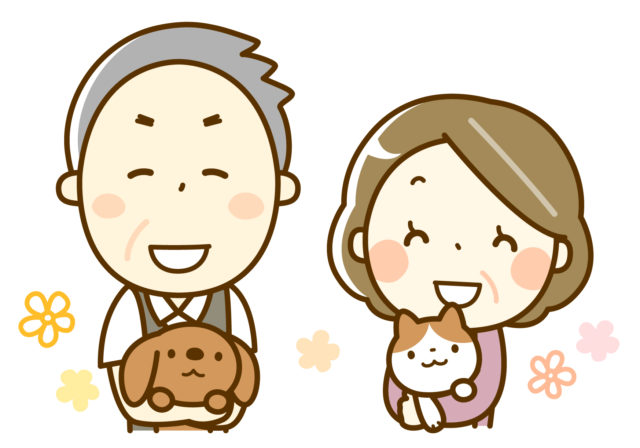
中には、動物の癒し効果を期待して、支援活動を行っている団体もあります。
「ドッグセラピージャパン」と、障がい者グループホーム「わおん」です。
先にご紹介するドッグセラピージャパンでは、アニマルセラピーの効果を理解し、心豊かな社会を目指して活動を行っています。
ドッグセラピージャパンの活動内容はたくさんありますが、ここでは一部を紹介します。
- 各種福祉施設を訪問
セラピー犬が活躍する主な場所で、人々に笑顔や生きる勇気を与えます。
- セラピー犬とふれあえるカフェ
犬を飼いたくても飼えない方にも、犬とふれあえる時間をつくっています。
- セラピー犬の学校訪問
犬を通して、子どもたちに命の大切さや自然への配慮を伝えています。
つづいてご紹介する、障がい者グループホーム「わおん」では、アニマルセラピーの効果を期待した取り組みを実施しています。
保護犬や保護猫を迎え入れ、障害や病気があっても、当たり前に動物と一緒に暮らせる地域社会を実現しようという取り組みです。
ペット共生型の福祉施設であり、ここでもアニマルセラピーの効果が期待されていますよ。
詳しくはこちら。
アニマルセラピーの問題点
アニマルセラピーは犬や猫をはじめとした動物が、人に対して良い効果をもたらす療法ですが、問題点や課題もあります。
セラピーという目的のために動物は多くの人と接します。
そのため、単なるペットとして暮らすよりも多大なストレスや疲労を感じてしまう恐れもあります。
人と会わない時間を意識してつくってあげるなどの注意が必要です。
また、施設を訪問する動物は、エサをもらいすぎたり、散歩の時間を取れなかったりすることがあります。
これらは運動不足や肥満につながる可能性があります。
アニマルセラピーを行う場合、動物だけでなく、セラピーを受ける人側も気をつけたいポイントがあります。
それは、感染症やアレルギーです。
アニマルセラピーとして活動している動物は基本的に予防接種をしていますが、それでも感染症や衛生面には注意したいところ。
動物アレルギーがないかどうかを前もって確認しておくことも重要です。
また、状況によっては噛みつかれたり、ひっかかれたりすることもあります。
「訓練されているから大丈夫」と、動物に負担をかけるような行動をしないようにしましょう。
まとめ
アニマルセラピーは、医療・福祉・介護などさまざまな場所で効果を発揮しています。
アニマルセラピーの効果についてはまだ証明されていないことも多く、その分可能性を秘めているといえます。
動物とともに暮らせる社会は、心豊かな生活を実現させるでしょう。
「いえらぶポータル」ではペット可物件やペット共生型賃貸物件をご紹介していますので、ペット可賃貸をお探しの方はぜひご覧ください。