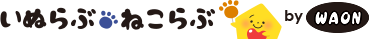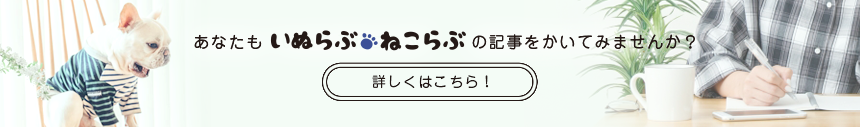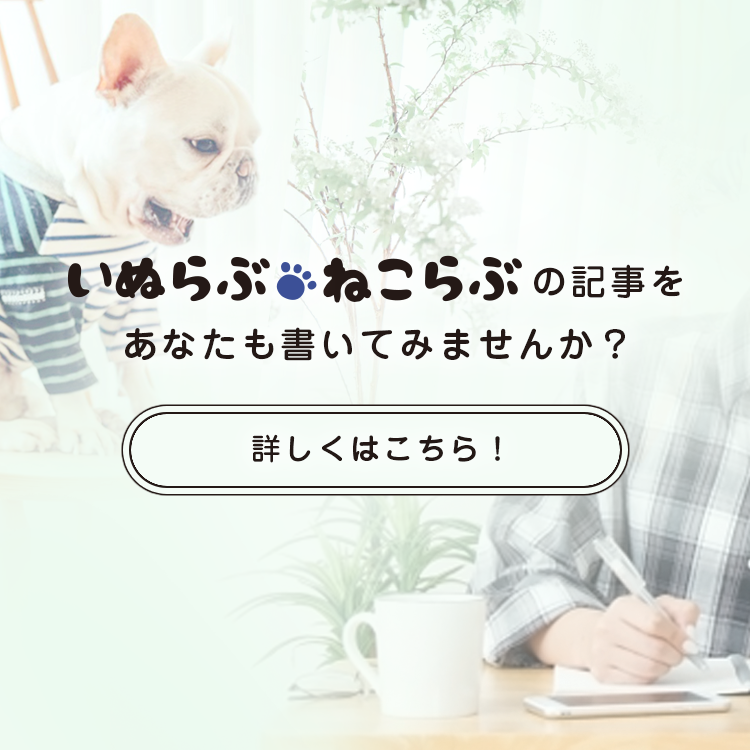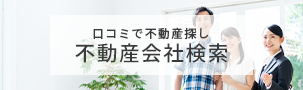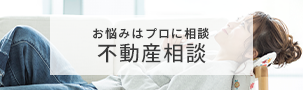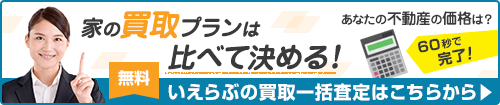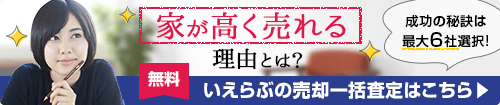目次

ペットの王道といえば犬と猫。
犬は人懐っこくてかわいいし、猫の鳴き声や甘えてくる姿もかわいいですよね。
犬派か猫派かなんて言われるけど、どっちかなんて選べない!
どっちとも暮らしてみたいという方いませんか?
そこで今回の記事では、犬と猫を一緒に飼うときのポイントをご紹介します。
ペットも飼い主も、みんなでなかよく暮らす方法を一緒にみつけましょう!

犬と猫の習性について
まずは、犬と猫の習性をみてみましょう。
「犬と猫は全く別の生き物である」
という前提を頭に入れておくことは、一緒に飼う上でとても重要です。
最近では、SNSなどで犬と猫がお互いに仲良く寄り添っている画像や動画をよくみかけ、ほっこりしますが
「全ての犬と猫が必ずしも仲良くなるわけではない」
という認識をしておきましょう。
<犬の習性>
犬は、オオカミのように群れで生活する動物だといわれています。
獲物を捕まえるときも、敵から身を守るときも、基本的に群れで行動します。
そのため、群れの仲間である家族を大切にする傾向があります。
もちろん、飼い主のことも家族として認識し、一緒にいることやふれあいを求めます。
愛情深く、社交的。
飼い主との時間をたくさん過ごしたい、寂しがり屋さんともいえますね。
群れで活動するので、リーダーに従うという本能もあるのが犬の特徴。
飼い主をリーダーとして認識するため、従順にふるまいます。
<猫の習性>
猫は、猫同士でも群れをつくることはなく、単独で行動する動物だといわれています。
マイペースで、自分の時間を大切にしたいという特徴もあります。
家族とのにぎやかな生活を好む犬とは異なり、猫は、自分の空間のある落ち着いた時間を求めます。
基本的に単独ですが、甘えたいときもあるのが猫のかわいいところ。
いわゆるツンデレですね。
また、昼間に活動する犬とは異なり、昼はほとんど寝て、夜に活動するという習性もあります。
比べてみると、犬と猫ってけっこう正反対なんですよね。
それぞれに合った生活スタイルに配慮しながら暮らすことがポイントとなりそうです。
どっちから飼うべき?タイミングはある?

<どっちも同時に飼う場合>
どっちも飼うと先に決めているのであれば、同時に家に迎え入れるという方法もあります。
犬と猫には、それぞれ社会化期とよばれる時期があります。
社会化期とは、その名の通り「社会」について学んでいく時期です。
この時期では、親や家族とふれあいながら、他の動物とのかかわり方や狩りの方法を学びます。
この時期に一緒にいると、お互いを仲間として認識するので仲良くなりやすい傾向にあります。
個体差はありますが、犬の社会化期は生後3週~16週くらいで、猫の社会化期は生後2週~9週くらいだといわれています。
同時に飼うなら、お互いが子犬、子猫の時期がよさそうです。
ただし、飼い主がペットのお世話に慣れていないと、子犬と子猫を同時に飼うのは難しいこともあります。
飼い方についてしっかりと勉強できる時間や、お世話をする時間を多めに取れるようにしましょう。
<成犬がいる家庭で新しく猫を迎え入れる場合>
上で述べたように、犬には「群れをつくる」という習性がありますから、飼い主が迎え入れた新入りの猫も仲間として大切にする傾向にあります。
また、子猫の場合、自分よりも下の存在として認識し、面倒をみるという場合もあるんだとか。
比較的安心できるのがこのパターン。
ただし、成犬が子猫を噛んでしまったという報告もあるので、しつけには気をつけましょう。
成猫を迎え入れる場合、けんかに発展することもあるそうです。
お互いの性格や相性を考えたうえで、家族として迎え入れるかどうかを決めた方がよさそうです。
<成猫がいる家庭で新しく犬を迎え入れる場合>
ちょっと注意が必要なのがこのパターン。
猫は、自分の縄張りである家にやってきた犬を警戒します。
これは猫の習性からも分かるように、猫は群れて生活する動物ではないため、猫同士でも一緒に暮らすのは難しいといわれているからです。
品種にもよりますが、犬となれば、さらに難しくなるでしょう。
また、飼い主が、新しく迎え入れた犬ばかり可愛がってしまうことにも注意が必要です。
お世話は、先に飼っていた成猫を優先してあげましょう。
そうすることで、新入りの犬が「最初から住んでいた先輩猫が優先」と認識できます。
また、後から来た犬ばかりにかまってしまうと、嫉妬やストレスを感じる猫も少なくありません。
必要なものとは

いざ、一緒に暮らすことになったら必要なものとはなんでしょう。
予防接種の手続きは各自治体が発信しているので、サイトなどで確認しておきましょう。
また、動物病院にお世話になった際、想像以上に高額な治療代を自己負担しなければならないというケースもあります。
ペットには公的な医療保険が適用されません。
そのため、ペット保険に入るという方は、その手続きも忘れないように注意しましょう。
手続き以外で必要になるものとしては、以下の通りです。
<犬にとって必要なもの>
- ハウスやケージ
- トイレシート
- 専用の食器
- 散歩用のハーネスやリード
犬は狭い場所を好む傾向があります。
屋根付きのハウスや、廊下の隅にケージを置くなど犬用の空間をつくってあげましょう。
また、トイレは犬専用のシートを用意してあげてください。
猫用の砂トイレは、食べてしまう危険があるので、トイレの場所を離すなど注意が必要です。
<猫にとって必要なもの>
- キャットタワー
- 猫砂
- 猫専用の食器
- 首輪
- 爪とぎ
猫は高い場所を好む傾向があります。
キャットタワー、棚の上にクッションを置くなどして猫が安心できる部屋をつくってあげましょう。
猫は、必要以上に犬がかまってくるのをストレスに感じることもあります。
犬がやってこられない専用スペースをつくることも、一緒に暮らすうえでポイントとなりそうです。
また、猫は爪がとがっているので、犬を傷つけないためにも爪とぎは必要です。
意外と見落としそうになるポイントなので注意しましょう。
初対面のとき
初めて会うときは誰だって緊張するものです。
警戒もします。
そこから、だんだんと距離が近くなっていき、お互いの臭いをかぎ始めたらコミュニケーション開始の合図。
このとき、威嚇をしたり、手が出るなど攻撃的な態度を取るようなら注意!
しばらくは距離をとって、様子をみましょう。
仲良くさせたい気持ちは分かりますが、無理に近づけないようにしてください。
犬にとっても猫にとってもストレスです。
まずは、お互いがプライベートで過ごす空間を分けることから始めましょう。
後に迎え入れた犬(または猫)が家に慣れてくるまでは、しばらくそのままで。
時間が経ってきたら、離れた位置からお互いの姿をみせたり、相手の匂いのあるものを近づけてみましょう。
徐々に相手を受け入れてくれる可能性が高まります。
ポイントは焦らず少しずつ機会を増やしていくこと。
注意点のまとめ
習性やタイミング、準備の紹介をしてきました。
ここで、注意点をまとめてみましょう。
<習性・対面時>
- 互いの性格や相性を考慮する(プードルやゴールデンレトリバーなど、比較的猫と仲良くなれる血統種もある)
- プライベート空間を分ける(留守中や目が届かない夜に起きるトラブルも防げます)
- とにかく焦らずゆっくりと(無理になかよくさせようとせず、お互いが同じ空間にいてもリラックスできるような関係性をめざす)
- 迎え入れる順番によって接し方を工夫してみる(同時に迎え入れる場合は一緒に遊ばせてみたり、子犬を後から迎え入れる場合は猫を先輩として認識してもらうなど)
<食事>
- それぞれ専用の食器を用意する
- エサの時間をずらす
- エサを置く場所を分ける
犬は基本的になんでも食べる雑食な動物。
一方で猫は肉食です。
体に合わないものを食べてしまうと、病気になる可能性があります。
そのため、お互いのエサを食べてしまわないように工夫する必要があります。
<その他注意点>
- トイレはそれぞれ専用で分ける(一般に犬はトイレシーツで、猫は猫砂です。習性が違うという認識を忘れずに)
- おもちゃはそれぞれ準備する(取り合いになってケンカするのを防ぎます)

まとめ
いかがでしたでしょうか。
どっちも好きな犬と猫。
一緒に暮らすならお互いなかよくしてほしいと思うのが、飼い主の気持ちですよね。
しかし、無理やり近づけてはいけません。
同じペットといっても、やっぱり違う動物同士。
犬と猫を一緒に飼うときは、お互いがストレスを感じることなく暮らせるように配慮してあげましょう。
「いえらぶポータル」ではペット可物件やペット共生型賃貸物件をご紹介していますので、ぜひご覧ください。