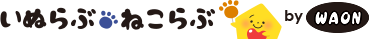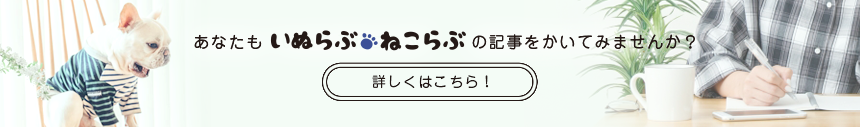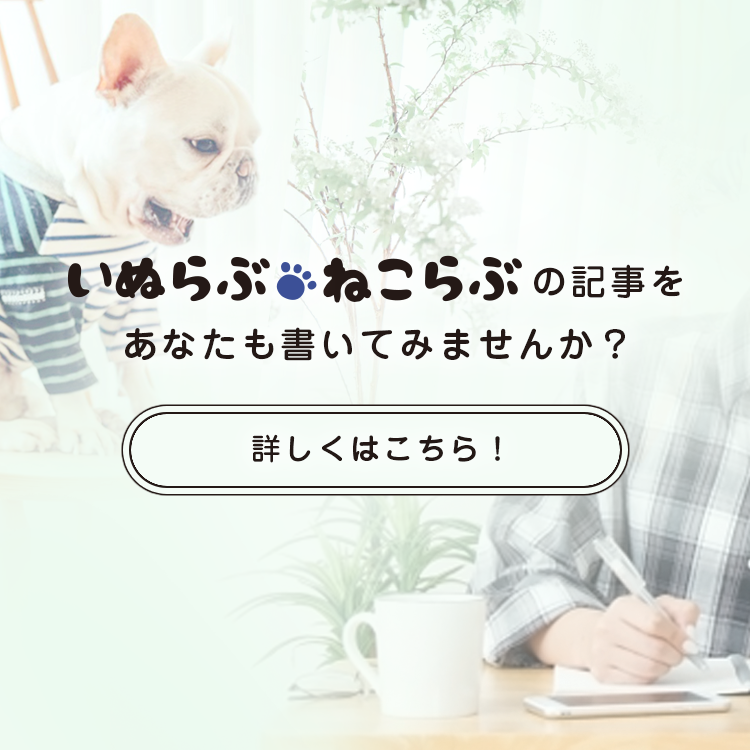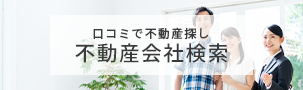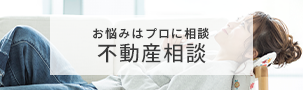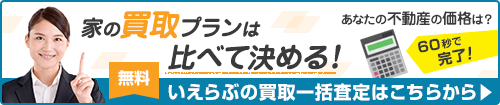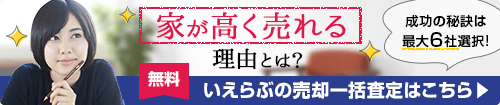目次
ペットが急にご飯を食べなくなると、飼い主としては不安になりますよね。
「どのような対処法を取ればいいのかわからない」と心配になるでしょう。
ご飯を食べなくなる理由はさまざまで、それによって対処法も異なります。
この記事では、ペットの食欲不振の原因と対処法、注意点についてご紹介します。
ペットがご飯を食べないときの原因

ペットがご飯を食べない原因は以下のことが考えられます。
体調不良
まずは、ペットの体調不良を疑いましょう。
ただ単に夏バテや季節の変わり目による体調不良の場合や、病気の可能性も考えられます。
病気の場合は、すぐに異変に気づいてあげることが重要です。
- 下痢や血便、嘔吐の症状がある
- 歯茎が腫れている・口臭がする
- 咳が多く、息がしづらそう
- いつもより元気がない
このような症状がある場合は、注意が必要です。
ストレス
犬や猫は、ストレスが原因でご飯を食べないことがあります。
しかし、ペットは飼い主にストレスを感じていることを伝えられません。
そのため、ペットの最近の様子や出来事を振り返り、ストレスを感じていないか考えてみましょう。
- 環境の変化
- 留守番の時間が増えた
- 飼い主と離れることがあった
- 普段と違うことをした
このような状況ではペットがストレスを感じることがあり、犬や猫の種類によっては神経質な子もいるのでペットたちの気持ちに寄り添うことが大切です。
老化
人間と同じようにペットも年齢を重ねると、だんだんと食べる量が減っていきます。
成長期を過ぎると食べる量が落ち着き、老犬や老猫になると消化がしやすいものを好むようになります。
とくに、歳をとったペットが食べなくなると不安になると思いますが、カロリーが高いご飯に変えると肥満の原因にもなるので、年齢に合わせたものを与えることが大切です。
好き嫌い
ご飯の切り替え中に違う味に反応して食べなくなったり、反対に同じご飯に飽きて食いつきが悪くなったりすることがあります。
また、ご飯は食べないけどおやつは食べるという場合は、ご飯の好き嫌いをしている状態だと言えます。
とくに、ご飯を食べないでいるとトッピングが増えたり、新しいご飯が貰えたりすると学習しているペットに多く見られますよ。
しかし、加齢によって味覚が変わっていることや、味を感じにくくなっているケースも考えられるので、ペットの年齢や状況に合わせて判断するようにしましょう。
ホルモンの乱れ・発情期
季節による理由で、意図的にご飯を食べない場合があります。
春や秋は一般的に発情期を迎える時期で、ホルモンの乱れとともに食欲不振になることも。
その場合は、いつもより攻撃的になるので、食欲不振以外にこのような行動がないかどうか確認してください。
また、体温保持のために冬の間に貯えた脂肪を、暑くなる夏に向けて落とそうとしていることも考えられます。
食べる量が減っている場合は、このような季節的な要因も関係していることがあると理解しておきましょう。
ペットがご飯を食べないときの対処法

ご飯を食べなくなったら、その原因に合わせて適切に対処することが重要です。
以下の対処法を試してみてくださいね。
動物病院に相談する
食欲にムラがあったり、排せつがきちんとできていたりする場合は、まずは数日様子を見てもよいでしょう。
しかし、まったく食べないときや元気がないときは、病気や体調不良の可能性があります。
無理にご飯を食べさせようとはせず、できるだけ早く動物病院に相談しましょう。
遊ぶ時間を増やす
ペットがストレスを感じて食べない場合は、遊ぶ時間や一緒に過ごす時間を増やすことが効果的です。
飼い主とあまりコミュニケーションをとれていないと、ペットは不安やストレスを感じてしまうことがあります。
一緒に過ごしてあげることで、ペットを癒すことができますよ。
またご飯を食べないからといって大きな声で叱ったり、しつけようとしたりするのは、やめましょう。
ペットがさらにストレスを感じてしまい、ますます食べなくなってしまいます。
大切なのは、ストレスの要因を取り除くことやコミュニケーションを取ることですよ。
ご飯に工夫する
もしご飯の切り替えがうまくいかないときや老化によって食べられない場合は、与えるご飯の工夫が必要です。
たとえば、ご飯の切り替えの際には前のご飯と新しいご飯を混ぜて与えてみたり、少しだけご飯に魚や肉などのトッピングを加えてみたりしてみましょう。
また、加齢によって食いつきが悪くなっている場合はぬるま湯でふやかしたり、ご飯を温めて匂いを強くしたりするのがおすすめです。
ペットの好みや反応に合わせて、ご飯をアレンジしてみてくださいね。
一方で、おやつだけを食べるときは飼い主に甘えている可能性があります。
その場合は一定期間おやつをあげずに、ねだってきても褒めたり、なでたりしないようにしてください。
「可愛いね」と褒めてしまうと、おやつだけを食べることが悪いと認識できなくなってしまいます。
運動量を増やす
運動不足や代謝の低下はそのまま食欲不振につながり、さらに、他の病気の原因にもなる可能性があるので注意が必要です。
散歩の距離や時間、頻度を増やしたり、室内での遊びを積極的に取り入れてみたりしてください。
運動させることで空腹になり、食欲の回復が期待できますよ。
ペットがご飯を食べないときの注意点

ペットがご飯を食べない場合は正しい対処法を取ること以外に、注意点も把握しておくと安心です。
食べない期間は2~3日間まで
ご飯を食べなくなると、「このままで大丈夫だろうか?」と心配になりますよね。
食べないことで健康が損なわれたり、元気がなくなったりするのではと不安を感じるでしょう。
ペットの状態にもよりますが、まずはどのくらい食べていないかを確認してください。
一般的に食欲不振以外の症状がない成犬・成猫の場合は、2~3日は様子を見ても問題はないでしょう。
しかし、まったく水を飲んでいないときや老犬・老猫で体力が弱っているときは、早めに対処しましょう。
また、普段から通っている動物病院で、ご飯を何日間食べなくなったら受診をするべきか確認にしておくこともおすすめですよ。
水の摂取量を確認
ご飯以外にも水は飲めているのかどうかも、必ず確認するようにしてください。
水を飲まないでいると、脱水症状をおこしたり尿路結石症を発症したりします。
また、脱水は急性腎臓病などの病気の原因になることも。
数日で病気が進行し命が危険にさらされるので、水分の摂取量は普段から注意深く観察してくださいね。
ご飯のトッピングは調節する
ご飯にトッピングを加えることで食欲が戻ることも多いですが、与える量には注意が必要です。
あまりにもトッピングを豪華にしすぎると、ペットが学習してしまい、わざと食べなくなる場合があります。
また、魚や肉、チーズの量が増え、カロリーが増えすぎたり栄養バランスが崩れたりすることも。
かえってペットの健康を害することにつながるので、ご飯を食べないからといって、トッピングを増やし過ぎないでくださいね。
まとめ
今回は、ペットがご飯を食べないときの原因や対処法をご紹介しました。
ご飯を食べないと病気かもしれないと、心配になりますよね。
しかし、様子をよく観察し正しく対応することで、ペットの健康を守れるでしょう。
大切な家族であるペットの気持ちに寄り添い、ぜひ健康的な生活が送れるようにしてあげてくださいね。