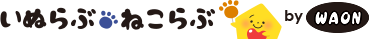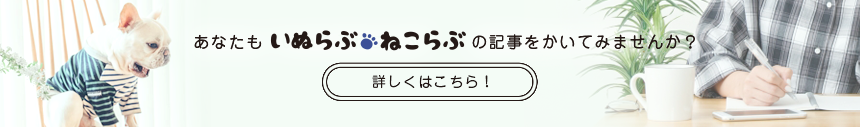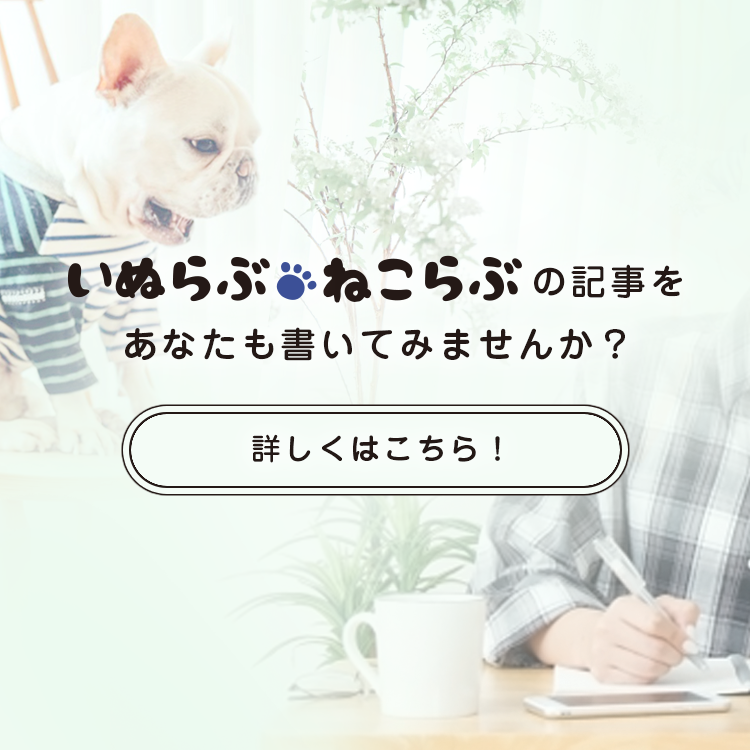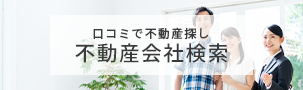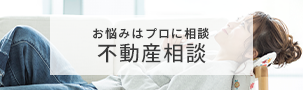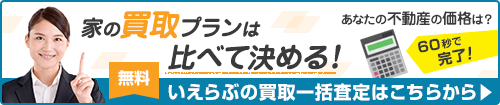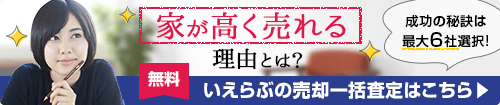目次
先日、障がい者施設で虐待事件があったと報道されたのをご存知ですか?
施設の元職員が、重度の障がいがある男性に傷害・暴行をおこなったとして逮捕された事件です。
参考サイト:NHK WEB NEWS 障害者施設で虐待疑い元職員逮捕 10月13日
今後、施設での労働環境や、障がいのある方との向き合い方などは、社会全体で考えていかなくてはならない問題です。
そこで今回は、障がい者施設で起こる虐待の原因とそれを防止するための対策をまとめてみました。
福祉施設の当事者以外にも、ぜひ読んでほしい内容となっています。

障がい者が虐待を受けている実態について
まずは、障がい者の虐待の実態をみてみましょう。
厚生労働省が発表したデータによると、障がい者施設の職員による虐待の相談・通報件数は、平成 30年度で2,605件でした。
平成29年度の2,374件から10%増加しています。
相談・通報件数が増加しているのは、周囲の方々が「虐待かもしれない」と気にかけることが増えたとも考えられます。
相談件数などが増えるのが、一概に悪いとはいえないんですね。
そこで、実際に虐待と判断された件数を見てみると、平成30年度は592件。
これは、データが記載されている平成24年度以降、最多の件数となっています。
虐待判断件数が増加しているのは、見過ごせない状況ではないでしょうか。
虐待の種類の内訳はこちらです。
身体的虐待…52%
心理的虐待…43%
性的虐待…13%
経済的虐待…7%
放棄、放置…6%
また、被害に遭っている75%が知的障がい者です。
考えられる要因として、意思表示がうまくできない、職員の言いなりになってしまうなどがあげられるでしょう。
参考サイト:平成30年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)を公表します 令和元年12月20日
内訳にもあるように、虐待の種類は主に5つに分類されています。
1.身体的虐待
殴る、蹴る、縛り付ける、閉じ込めるなど
2.心理的虐待
怒鳴る、仲間外れにする、子ども扱いする、無視をするなど
3.性的虐待
性的な行為や接触を強要する、障がい者の前でわいせつな会話をする、わいせつな行動をさせるなど
4.経済的虐待
当人の同意なしにお金を処分・運用する、日常で必要なお金を渡さないなど
5.放棄・放置
飲食を与えない、介助をしない、病院に受診させない、第三者による虐待を放置するなど
施設でおこる虐待の特徴は、身体的拘束や暴行、暴言などが目立ちます。
いずれも共通しているのは、「障がい者が思い通りに動かないから」「言うことを聞かないから」といった理由によるもの。
虐待の加害者が「しつけ」や「指導」のひとつだと思っており、虐待と認識していない場合もあります。
そのときは第三者の存在が重要です。
障がい者虐待防止法では、発見者に通報義務を課しています。
通報したから解雇されたなどの不利益を受けることはありません。
もし、施設内で虐待が起きているかもしれないと思ったら、外部の機関に相談してみましょう。
なぜ福祉施設で障がい者虐待が起こるのか
ここまで虐待の実態についてみてきましたが、なぜ福祉施設の職員が虐待をするのか疑問に思った方はいませんか?
一般に、看護師や介護士、ヘルパーさんといった医療・福祉に携わっている方には、やさしいイメージをお持ちですよね。
奉仕の精神があるやさしい心の持ち主…。
- 全員ではないにしても、多くの職員さんがそのイメージに当てはまると思います。
ではなぜ、そのような方々が虐待事件を起こしてしまうのか。
考えられる原因は主に3つです。
<障がい者福祉施設が閉鎖的空間であること>
ひとつは、施設が閉鎖的な空間であるから。
施設が、人里離れた場所に建てられることは珍しくありません。
また障がい福祉施設は、社会から孤立した閉鎖的な空間であることも多く、そうした場所には他人の目が入らないため事件が隠されやすくなるのです。
閉鎖的な施設の特徴はこちら。
- 日中、障がい者は外に出ず、施設内で活動をおこなう
- 身内の来訪が少ない
- 施設の管理者なども別室で事務作業をおこなっている
このような孤立した場所でストレスがたまり、その発散が障がい者自身に向けられるのです。
<職員の労働環境が悪い>
もうひとつは、施設職員の労働環境の待遇が悪いこと。
医療や福祉の世界は常に人手不足だといわれており、障がい者福祉施設もあてはまります。
あちこちで求人を見かける方も多いのではないでしょうか。
その求人情報をよく見ると、安い賃金が提示されていることに気づくと思います。
安い賃金が福祉施設での仕事内容に見合っていないことから、離職につながるケースもあるんです。
思いやりの心だけでは生活できません。
仕事である以上、お金は必要です。
このように、金銭的に余裕がなくイライラがたまり、虐待へとつながる部分もあります。
また、収入面だけでなく、精神的にもストレスがたまりやすい職場だといえます。
食べるのが遅い障がい者や、思うように動いてくれない障がい者、ときには職員自身が彼らに殴られることも…。
それでも我慢して、「仏の心で支援しなければならない」と重圧を受けて働いている職員さんたちがいるのです。
これに閉鎖的な空間が相まって、誰にも相談できず爆発してしまい虐待へつながるケースもあるでしょう。
<障がい特性の知識不足>
「仕事として障がい者を相手にしている方なら、ある程度知識をもっているのでは?」
という考えも否定できません。
ですが、先ほどもお話したように高齢社会の日本では、全体的に働き手が不足しています。
福祉施設も例外ではありません。
人材確保に忙しいため、すぐに動けるのであれば、特別な資格をもっていなくても支援員として働ける職場なのです。
もちろん資格をもっている職員もいますが、全員がそうだとは限りません。
むしろ、資格を持っている方はもさらに給料のいい環境に就職するため、現場は悪循環になっているのです。

施設での障がい者虐待を防止する方法とは?
最後に、施設での虐待を防止するにはどのような取り組みをするとよいのかご紹介します。
<施設を開放的にすること>
虐待がおこる原因のひとつでもある施設の閉鎖性を改善することで、虐待防止が期待できます。
ボランティアや研修生などを積極的に取り入れたり、障がい者が地域の方々と交流できるようなプログラムを作成したり…。
外部と開放的なつながりをもつことが虐待防止には必要です。
しかし、現在のコロナ禍により、対面での交流は実践できていないのが現状だと思われます。
施設での虐待事件が浮き彫りになってきた実態も、コロナによる影響があると推測されます。
これからどのように開放的な空間をつくっていくか、新しい策を考える必要があるでしょう。
<障がい者自身が虐待について知ること>
被害の多くは知的障がい者が占めています。
障がい者の中には、虐待されていること自体に気づいていないケースも多くあるのです。
そのため、まずは障がい者自身が「今されていることは虐待なんだ」と気付ける状態になった方がよいでしょう。
自分だけで気付くのは難しいため、外部からの働きかけも大切になってきます。
ある福祉施設などでは、研修会や講演会などで講師を呼んで、自分の権利を学ぶ機会をつくっています。
<声をあげやすい環境づくり>
障がい者自身が虐待について理解するだけでなく、実際そのような状況になったら声をあげるのが望ましいです。
しかし、話せないなどの物理的な問題もあれば、「誰かに相談したとばれたら、さらに虐待されるのではないか」といった精神的な理由からSOSを出せない被害者もいます。
虐待を隠さないためにも、声をあげやすい施設づくりを意識するとよいでしょう。
それは障がい者だけでなく、そこで働く職員のためにもなります。
相談できる相手とすぐにコンタクトをとれる環境だったり、カウンセリングを身近に受けられる職場だったりすると、虐待について打ち明けやすくなるでしょう。

まとめ
施設で働く職員の環境を考えると「自分は絶対に虐待なんてしない」と簡単にいいきれません。
今後社会全体で障がい者が虐待されないような社会づくりを造っていかなければいけないのです。
施設を開放的にすることとは、社会全体で受け止めること。
私たち全員で考えなければならない問題だといえます。