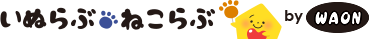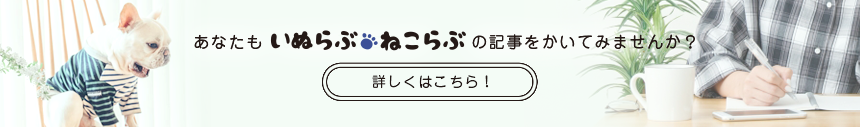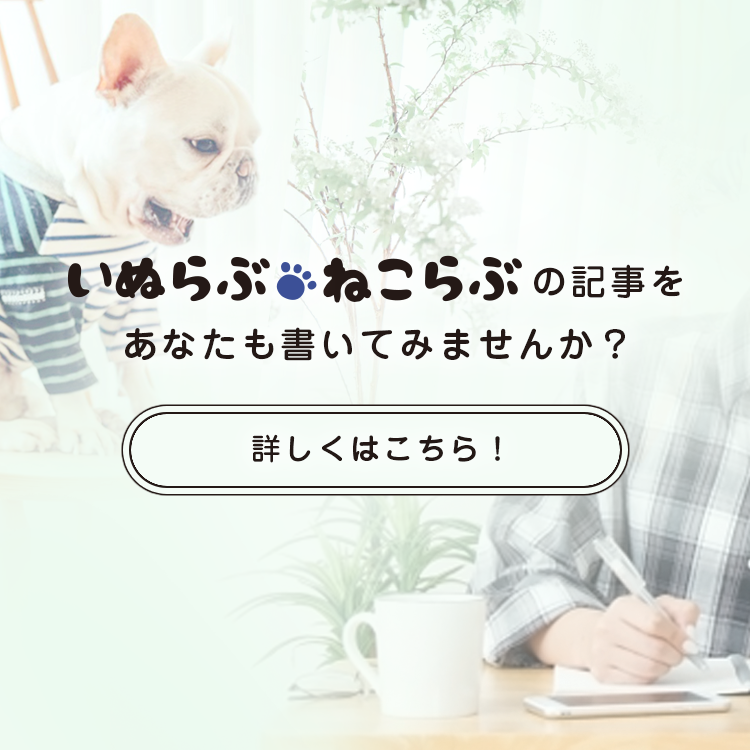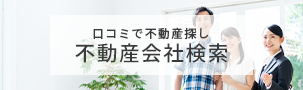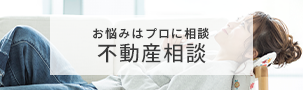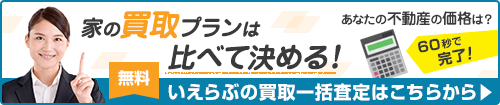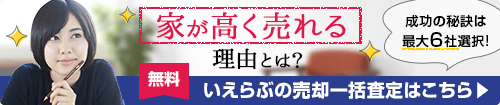目次
年末年始のごちそうやコロナウイルス感染防止による自粛生活で、「つい、食べすぎちゃったな」と考えている方はいますか?
体重の管理は、意識しないと難しいですよね。
それは犬や猫にとっても同じことです。
ペットの体重管理、しっかりできていますか?
今回はペットと肥満についてのお話です。
ペットの肥満にはどんなリスクがあるのか、そして肥満対策の方法もご紹介していますよ。
犬や猫はどれくらい太ると肥満なのか

犬や猫の肥満度は、BCS(ボディコンディションスコア)とよばれる方法で確認できますよ。
BCSは見た目と感触から体型を5段階、または9段階に評価する方法です。
5段階評価の際は、BCS3を標準として考えます。
環境省が犬と猫のBCSと体型を紹介していますので、引用してご紹介します。
犬のBCSと体型
- BCS1(痩せ)
肋骨、腰椎、骨盤が外から容易に見える。
触っても脂肪が分からない。
腰のくびれと腹部の吊り上がりが顕著。
- BCS2(やや痩せ)
肋骨が容易に触れる。
上から見て腰のくびれは顕著で、腹部の吊り上がりも明瞭。
- BCS3(標準体重)
過剰な脂肪の沈着なしに、肋骨が触れる。
上から見て肋骨の後ろに腰のくびれが見られる。
横から見て腹部の吊り上がりが見られる。
- BCS4(やや肥満)
脂肪の沈着はやや多いが、肋骨は触れる。
上から見て腰のくびれは見られるが、顕著ではない。
腹部の吊り上がりはやや見られる。
- BCS5(肥満)
厚い脂肪におおわれて肋骨が容易に触れない。
腰椎や尾根部にも脂肪が沈着。
腰のくびれはないか、ほとんど見られない。
腹部の吊り上がりは見られないか、むしろ垂れ下がっている。
猫のBCSと体型
- BCS1(痩せ)
肋骨、腰椎、骨盤が外から容易に見える。
首が細く、上から見て腰が深くくびれている。
横から見て腹部の吊り上がりが顕著。
脇腹のひだに脂肪がないか、ひだ自体がない。
- BCS2(やや痩せ)
背骨と肋骨が容易に触れる。
上から見て腰のくびれは最小。
横から見て腹部の吊り上がりはわずか。
- BCS3(標準体重)
肋骨は触れるが、見ることはできない。
上から見て肋骨の後ろに腰のくびれがわずかに見られる。
横から見て腹部の吊り上がり、脇腹にひだがある。
- BCS4(やや肥満)
肋骨の上に脂肪がわずかに沈着するが、肋骨は容易に触れる。
横から見て腹部の吊り上がりはやや丸くなり、脇腹は窪んでいる。
脇腹のひだは適量の脂肪で垂れ下がり、歩くと揺れるのに気づく。
- BCS5(肥満)
肋骨や背骨は厚い脂肪におおわれて容易に触れない。
横から見て腹部の吊り上がりは丸く、上から見て腰のくびれはほとんど見られない。
脇腹のひだが目立ち、歩くと盛んに揺れる。
参考サイト:環境省「飼い主のためのペットフード・ガイドライン~犬・猫の健康を守るために~」
BCSがわかったら、体重と照らし合わせてみましょう。
適正体重は個体によって異なりますから、動物病院で検診をした際などに獣医さんへ確認するといいですよ。
体重は毎日や毎週測るのが理想ですが、少なくとも月に1回はチェックしておきたいところです。
測るタイミングは、同じ時間帯にするのがポイント。
ご飯の前と後、トイレの前と後などでは体重が変わってしまうからです。
朝起きてご飯を食べる前に測定するなど、ルーティンの中に組み込むといいかもしれません。
ここでは、ペットの体重を家で測れる方法をご紹介するので、ぜひ試してみてくださいね!
ペットの体重測定方法①
簡単なのは、飼い主と一緒に測る方法です。
まずは飼い主自身が体重計に乗り、測定します。
そのあと、ペットを抱っこして一緒に体重計に乗ります。
自分ひとりで測ったときと、一緒に測ったときの差がペットの体重とわかりますよ。
家にある体重計で測定できるので、手軽ですよね。
素直に抱っこさせてくれなかったり、大きくて抱っこが難しかったりといった場合は、キャリーケースを使ってみましょう。
ペットの体重測定方法②
犬用や猫用の体重計、スケールを購入して測定する方法もあります。
人用と違って、犬や猫が乗りやすい設計になっているのが特徴的です。
値段はペットの大きさや機能によって異なります。
3,000円前後で購入できる小型サイズの体重計もあれば、大型犬サイズのものになると2万円を超えるものもあります。
何kgまで測れるのか確認してから購入しましょう。
肥満になるとどんなリスクがあるの?
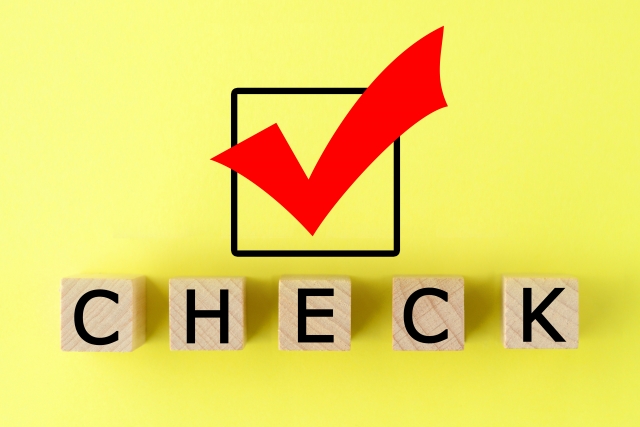
肥満は、犬や猫に健康上のリスクをもたらします。
肥満が原因で犬や猫に起こる病気として、このようなものがあげられますよ。
- 関節炎
- 椎間板ヘルニア
- 呼吸器系の病気
- 結石
- 内臓病
- 糖尿病
- 心筋症
- 脂肪肝、肝硬変
肥満になると、これらの病気のリスクが高まり、寿命を縮めてしまう可能性があるのです。
少し丸い姿が愛くるしく思えても、健康のためを考えると肥満は悪です。
そのため、愛犬や愛猫の肥満を許すのは、優しい虐待ともいわれています。
愛犬や愛猫には長生きしてほしいですよね。
肥満にならないよう日頃から対策しておくことをおすすめしますよ。
ペットはなぜ肥満になるの?犬や猫を肥満にさせない対策とは?

病気のリスクがあるとわかったら、肥満になってほしくないと願うのが飼い主の気持ちですよね。
いざ対策をしようと思っても、「なぜ肥満になるのか?」が分からないと手を打てません。
そこで、肥満になる原因を考えてから、対策方法を探していきましょう!
- 食事
エサを与えすぎると、もちろん太ってしまいます。
「ご飯は適量をあげている」と思っている飼い主さんも、一度立ち止まって考えてみましょう。
おやつを余分におねだりされたとき、「可愛いからつい…」と与えてはいませんか?
おやつは、ご飯と一緒に必要カロリーの中に入れて計算してから与えましょう。
年齢や体格に合わせた適切な食事を与えるよう心がけるといいですよ。
多頭飼いの場合は、ペット同士「食事の奪い合い」をしていないかチェックしましょう。
食事は、飼い主の目の届く範囲で与えるのが理想です。
いつでも食べられる状態にある置きエサなども、なるべく避けた方がよいでしょう。
また、避妊・去勢手術を済ませた犬や猫は、肥満になりやすい傾向があるといわれています。
繁殖に必要なエネルギー消費が減り、基礎代謝量が低下するためです。
避妊・去勢手術を済ませても、いつもと同じ量の食事を与えていると肥満になる可能性が高まります。
すでに肥満となっている場合は、肥満対策の療養のご飯を用意してもよいでしょう。
その際は、獣医師に確認をとってから与えてくださいね。
- 運動
摂取したカロリーを運動で消費しないことも、肥満の原因です。
そのため、散歩以外での運動する時間を作るようにしましょう。
しかし、普段はあまり動かない犬や猫が、長時間の運動を行うのはきついものです。
肥満の気になる体型で走り回る遊びをすると、ケガにもつながるかもしれません。
初めのうちは、やさしめの運動を数分ずつ行うようにしましょう。
犬の場合、散歩の時間を伸ばすだけでも運動とよべます。
猫は上下運動を好みますから、キャットタワーで遊ばせるのが効果的です。
「自分から運動しようとしない…」とお困りの方は、猫じゃらしなどのアイテムを使い、飼い主も一緒になって遊ぶなど工夫をしましょう。
すでに肥満となってしまった場合は、無理に運動すると関節を痛める危険があります。
そのため、食事改善を行うとともに、獣医師さんと相談しながら無理のない範囲で運動をしましょう。
直接的な運動が難しかったら、マッサージをしてあげるのもいいですよ。
リンパマッサージは、愛犬や愛猫とのコミュニケーションにもなります。
まとめ
愛犬や愛猫の体型を管理するのは、飼い主の役目です。
ペットが幸せそうにご飯を食べる姿は可愛らしく、微笑ましいです。
「おねだりされたら与えたくなる」
その甘さに流されてはいけません。
肥満になると、ペットとの幸せな時間が減ってしまうかもしれないのです。
食事や運動に気を配り、すてきなペットライフを過ごしてくださいね!